〜第三幕〜
『錯乱』
| 日々は、穏やかに過ぎていきました。 短い夏が終わり、秋になると、エルメイア様は城の中庭に積もる色鮮やかな落ち葉を集めて、宝物のように机や窓辺に並べていました。 しかし冬にさしかかり、冷たい風が吹くようになると、次第にエルメイア様の気はふさいできました。 日ごとに膨らんでいく胎をしきりに気にして、ついにはぽろぽろと涙を流し始めました。 誰だって母になることを不安に思うことはあるでしょう。乳母はエルメイア様の身体をさすりながら言いました。 「大丈夫、怖いことなんて何もありませんよ。エルメイア様はお母様になるのですから」 しわだらけの手になでられながら、エルメイア様はじっと聞き入っていました。 そしてお腹の赤ん坊が誰の目にも分かるほど大きくなる頃には、所構わず悲鳴を上げるようになりました。 エルメイア様はなんにも、分かっていなかったのです。 どうして皆が自分に優しいのか、どうしてキスをしてくれるのか。 母になるという、その言葉の意味さえ。 小さな子供が大人の口ぶりを真似て、そうすれば誉められることを知れば、何度でも繰り返すでしょう。 犬だって、主人の顔色をうかがって尾を振ります。 事の次第を理解するには、エルメイア様はあまりにも無垢すぎたのです。 やがてお腹の子が内側から胎を蹴るようになると、そのたびにエルメイア様は泣き叫びました。まるで背を毛虫が這ったように、身をよじり、とってくれとせがみました。 「いけません。いけません」 乳母は必死でエルメイア様にとりすがりましたが、癇癪はますますひどくなるばかりでした。 |
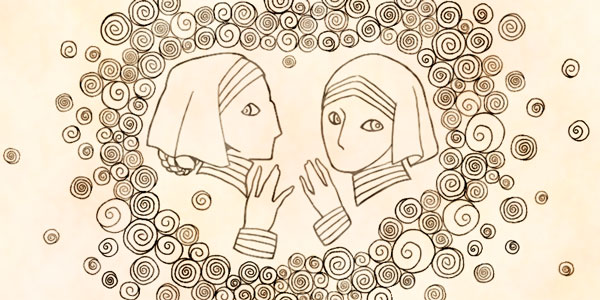 |
| 「奥様があんなに嫌がるなんて、きっとお腹の子は良くないものに違いないわ」 口さがない召使いの舌を、オブリード様は切り取ってしまいました。 唯一、オブリード様の腕に抱かれて眠るときだけ、エルメイア様の心に安らぎが訪れるのでした。泣きはらした目を閉じて、赤ん坊のようにオブリード様に身を預けました。 けれど辺境伯としてのお役目のために、オブリード様は城を離れざるを得ませんでした。 オブリード様がお留守の間に、エルメイア様が雪の降る晩に部屋から飛び出し、見つけられるまで何時間も外をさまよい歩いたことがありました。こんなことが続いてとうとう侍医は、お腹の子が十分に育つまでエルメイア様の腕と足を縛りつけておいてもいいかどうか、オブリード様に手紙を書きました。 |
| エデルカイト家の忠誠は王家にとって重要な後ろ盾の一つであったが、ジョルムント王がこれに応えて与えた娘は不具者であった。矛盾ともとれる王の采配には、いくつか説明が付けられている。 一つには、王の親族に年相応の娘がもはやエルメイア王女しか残っていなかったという致し方ない事情がある。他の王女はすでに他家に嫁いでおり、王太子の娘は嫁ぐには幼すぎた。王の手に残された駒は、白痴の姫君だけであった。 エデルカイト家による先の背反行為に対する懲罰ととらえる向きもあるが、王国の事情を考慮すると、まだ不安定な王家の存亡をかけてまでエデルカイト家に意趣返しをするつもりだったとは考えにくい。事実、釣り合いをとるかのように、ジョルムント王が娘に持たせた持参金は非常に高額であった。 エデルカイト家にも打算があった。王家の瑕瑾とも言えるエルメイア王女を引き受けることで、この婚姻交渉はエデルカイト家にとって有利な形となった。オブリード辺境伯は『諸部族の長』の称号を認められ、後に生まれた一人娘は下位ながら王位継承権を与えられている。さらに、オブリード辺境伯は王女が嫁いでのち、たびたび理由をつけては彼女の名で王家に資金の援助を求め、これを認められた。 そして、例え不具者であろうと、王族の血は彼にとって非常に魅力的な贈り物であった。すなわち大魔術師としての王族の能力である。異邦の魔術師であったジョルムントによる王位簒奪は、当時、大陸西部において勃興し始めていた近代魔術革命の先駆けであった。オブリード辺境伯は国内では禁忌扱いされていた魔術の導入に当初から積極的であり、婚姻関係を結ぶより前に、高名な魔術師の一団をホーゼンウルズに招き入れ、新技術の研究・開発を推奨、軍事力増強にあてていた。 読み書きや簡単な計算ですら不可能であったエルメイア王女が、魔術を扱えたはずもないが、強力な魔術師の血をエデルカイト家に導入するには十分であった。 王国内ではいまだ少数であった高位魔術師の数を増やそうとする王の思惑とも合致し、この婚姻は両家にとって満足のいくものとなった。 |